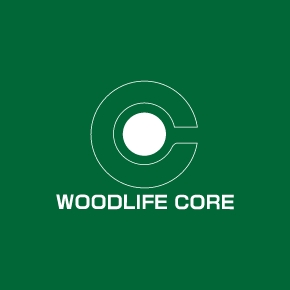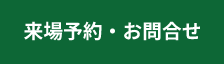夏の暑さも落ち着きをみせつつ、台風が毎週来そうで来ない、そんな秋のはじまりを感じる今日この頃。
秋は、五穀豊穣を願う祭りが各地で多く行われる時期でもあります。
本社周辺でも連日、太鼓練習のの音が聞こえてきたりもします。
私も9月10日・11日の2日間「百舌鳥八幡宮 月見祭」に参加しました。
もちろん、屋台を楽しみに行っただけ、ではなく、貴重な若い『担ぎ手』の一人として、
地域貢献に励んでまいりました。
この祭りでは、布団を積み上げたような形で『ふとん太鼓』と呼ばれる神輿型の台座を担ぎます。コロナウィルスの影響もあり、約3年ぶりの奉納が行われました。
各町毎に、公民館にふとん太鼓を格納する倉を所有しており、その倉から百舌鳥八幡宮まで練り歩き、境内、参道で盛大に担いで練り歩きます。
神輿の内部には、太鼓がロープで中空に吊りさげて内蔵されています。
神輿に乗った子供がそれを叩きます。
その太鼓の音にあわせて「べーら、ベーら」と声をかけながら、大人60~70人で力強く持ち上げます。
「べーら」とは、米良。良いお米ができますように、ということからきており、ここからも五穀豊穣を願っていることを表現していることがわかります。
大迫力、豪華、盛大、という言葉が似合う祭りというよりも・・・
「ふとん太鼓」は4人ほど子供を乗せ、神輿だけでもおよそ「3トン」とかなりの重量があります。
それを70人ほどの大人が、1歩1歩を確実に踏みしめながら歩き、朱色のふとん太鼓の響きに合わせて躍動する大房(白いふさふさ部分のこと)など、
勇壮・華麗さが見物人をじっくりと魅了する。ある種の上品さも兼ね備えた祭りといってもよい祭りだと、私は感じています。
ぜひ、来年の中秋の名月(月見祭と呼ばれる所以)の頃、堺にある300年以上の伝統の一つに足を運んでいただければと思います。実際にその場に立ち会ってもらえれば、きっと感じてもらえるのではと思います。そんな祭りです。
辻尾
いしやまの あきのつき つきにむらくも はなにかぜ かぜのたよりは あわのしま
しまのさいふに ごりょうじゅうりょう ごろごろなるのは なんじゃいな
じしんかみなり あとゆうだち べーらべーらべらしょっしょい
ぼたんにからじし たけにとら とらおうてはしるはわとうない
まとないおかたにちえかそか せんがんじのおじゅっさんは ぼんさんで
それゆえ はっさくあめじゃいな べーらべーらべらしょっしょい
「堺市・ふとん太鼓音頭」より