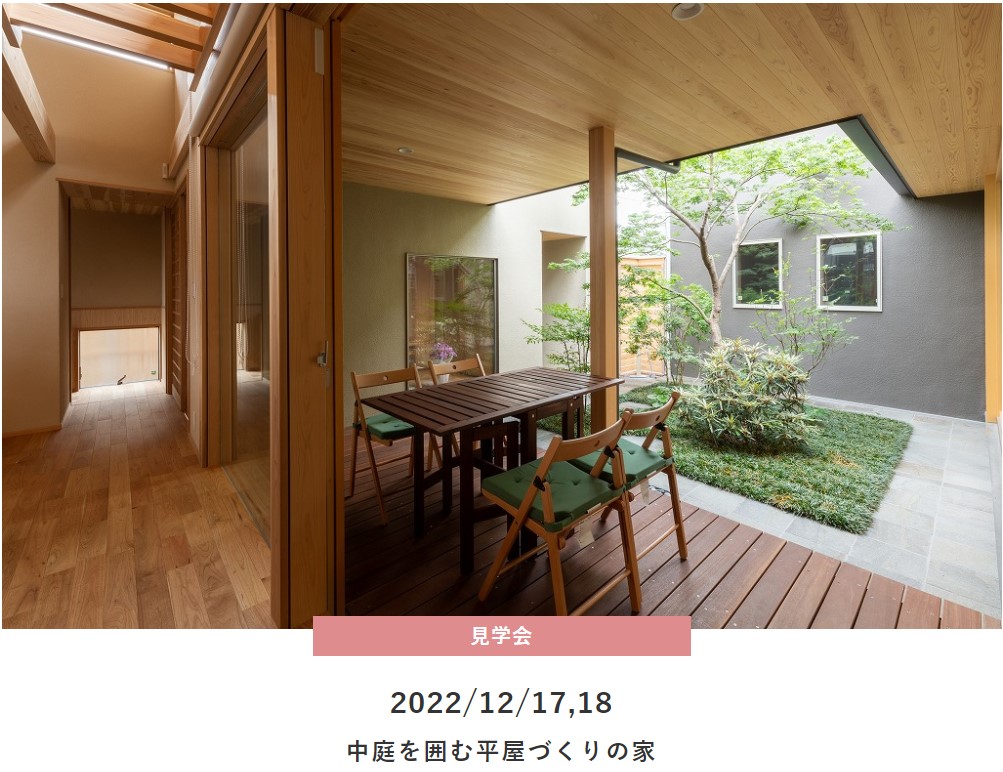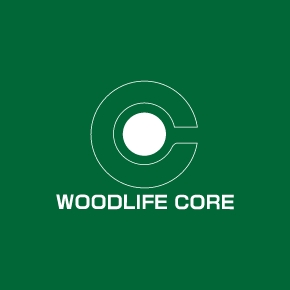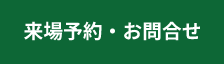出来上がったお家の床・壁・天井の下にはすべて下地となる木材が入っています。
土台敷きから上棟を行った際には家の骨組みが見える状態になりますが、工事が進み仕上げ工事に入るころには化粧材以外の木材は見えなくなり、壁の中などは二度と下地の状態は見られなくなります。
工事期間は長いようで短く、ご自身のお家が出来上がっていく過程を目にしておくことはとても素敵な思い出になると思います。
今回は、そんな見えないところで重要な役割を果たしている下地材についてお話をします。
①大引

コアー建築工房では、床は24㎜の構造用合板の上に15㎜のフロアーを貼って仕上げています。その下で床材を支えているのが大引です。大引に構造用合板を乗せて、ビスで打ち付けますので、基本的には土台のない箇所に910㎜の間隔で配置されています。
この大引は90角で、土台と同じくヒノキを使用しています。ヒノキを使うのは、床下空間の湿気や虫害に強いからです。
なお、大引は床下に潜るとその姿を見ることが出来ます。

②間柱

左官やクロスで仕上げる内壁の下には石膏ボードがあります。その石膏ボードは、左右の端と中心をビスで川の字に打ち付け留めています。そのビスを打ち付ける下地が躯体の柱と間柱です。

柱は一間(1820㎜)ずつ入ってることが多いのですが、石膏ボードは横幅が910㎜で、中通りにもビスを打ち付けるとなると、455㎜間隔で下地が必要になります。そのため、構造の120角の柱がない箇所や建物の隅の部分には、間柱を入れる必要が出てきます。
③天井野縁

天井を貼る部分には寸3角の角材を十字に這わせて下地を作ります。画像は車庫の天井ですが外部でも内部でも理屈は同じです。
洗面脱衣室などの水廻りなど、クロスなどで仕上げる場所には石膏ボードを、玄関などにはよく杉板を打ち付けています。

↓


(後藤)