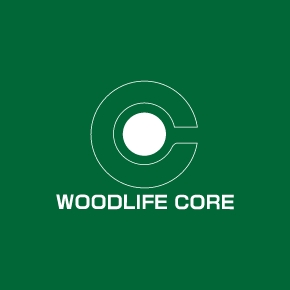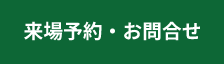木の家づくりをしているコアー建築工房では構造材に和歌山県の紀州材を使用しています。
今回は紀州材は森から伐採され、材木になるまでの流れを見学させていただきました!
その様子を少しご紹介します。
まずは伐採現場
木の伐採はチェーンソーと楔のようなものを打ち込んで1人で伐採するのだそう。
森で伐採された木はワイヤーで吊るされ、少し麓まで降りてきます。
そこで、こちらの機械が登場!

枝を落としながら、長さを測り、カットまでする優れものです。
この段階で太さや長さにある程度、仕訳けて市場へと運ばれます。
木材市場では太さと長さによって仕訳けられた木が“せり”に出されます。

この丸太に書かれている数字は丸太の直径の長さです。
木の先の太さで決まります。
直径の太さと長さによって、それぞれの木が何㎥あるかが決まり、1㎥あたりの単価によって木の値段が決まります。
ただ、太いから高いというわけではなく、木目の綺麗さや詰まり具合によっても金額は変わるそうです。
この市場でせり出された木が今度は木材屋さんへ
ここ、伸栄木材さんでは木の皮をはぐところから、製材、乾燥、強度試験までを行っています。


丸太1本を余すことなく使われています。
丸太の中心部分は柱や梁といった構造部分に。外側の部分は造作材と呼ばれる鴨居部分などや造作家具の材料として使われます。
木の皮や製材する際にでた切れ端は乾燥機を動かすためのボイラーの燃料に使われています。
また、ボイラーででた灰は和歌山県の名産品、梅を栽培する農家さんへと届けられます。梅を栽培する土壌にするのに灰が最適なのだそうです。
木材を和歌山県内で循環させるSDGsな取り組みをされていました。
今度は強度試験を見せていただきました。

写真では分かりにくいのですが、上から木材を押さえ、たわみ具合から木材の強度を調べるというものです。
1本1本押さえることで、表面上では分かりにくい内部の弱いところも確認できるそうです。
木材に求められる強度が平均E50というところを伸栄木材さんではE70からしか出荷しないというこだわりです。
今回は森の木が材木になるまでを見学させていただきました。
11月には材木がお家になるまでを見学できる「家づくりウォッチングツアー」を開催します!
大阪でお家づくりをご検討されている方はお気軽にご参加ください。